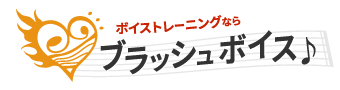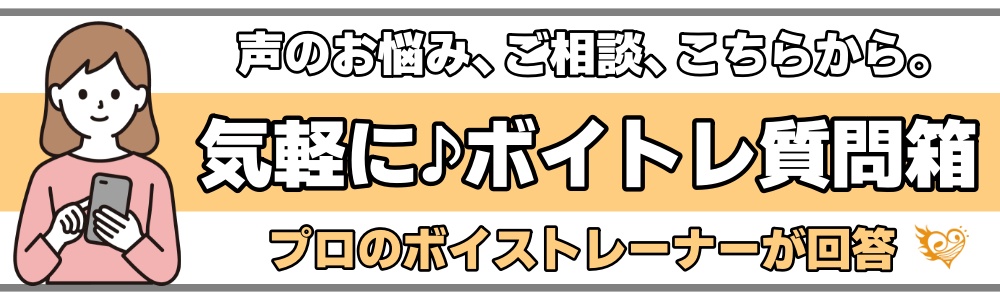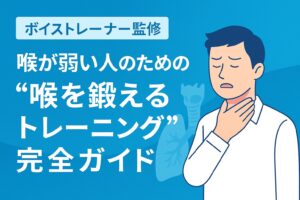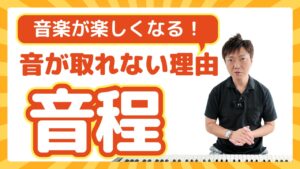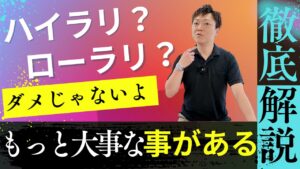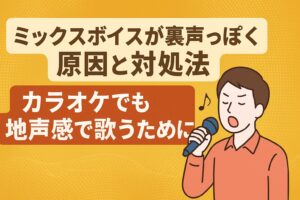いつもボイストレーニング、お疲れ様です。
ハモリを上手にコントロールするコツや自分でできる練習方法は何なのかと言うご質問を頂きました。
今回、割と上級者向けの回答内容なので、初級者向けでは全くありません、初級者の方はスキップしていただいても良いのかもしれません。
今回は玄人向けの回答として解説していきます。
先に結論を申しますと、「主旋律の3度上と3度下を取る癖をつける」というのが1番のコツになります。
自分でできるハモリの練習方法について
HN:K.A.
質問タイトル:声のハーモニーについて
はじめまして。
現在趣味でユニットを組んで活動を行っているのですが、いわゆるハモりというものが上手くできません。
音程はわかっているのですが、主旋律につられてしまい上手くハモることができません。
ひとりでもできる効果的なトレーニングはありますか?
また、自分がハモリパートを歌う際に気をつけるべきことはありますでしょうか?
宜しくお願いします。
今回は主旋律の3度上と3度下を取る癖をつけるにはどんな方法があるのかと言うのをご紹介したいと思います。
方法はズバリ2つです。
方法①コードに対して自分の音階がどこに行っているのか理解できる様にする。
方法②主旋律に対して自分の音階がどこに行っているのか理解できる様にする。
ちなみにkeyがCの場合、ミの3度上はソの音。
3度下はドの音です。
主旋律が動いていくわけですが、動いていく音階が上に行ったり下に行ったりする度に、ハモリのパートも主旋律に対して基本は上と下を行ったり来たりするわけです。
あくまでも基本です。
トレーニングと言うよりも理屈を理解することが大事でして、強いて言うならばこれがトレーニングです。
ところで、質問者様がおっしゃられているような「音程はわかっているけれども主旋律につられてしまいうまくハモれない」と言う部分に関しては、ミュージシャンとしての考え方からすると、おそらく納得できない方は世の中に多いんだろうと思います。
特にセミプロ以上のレベルで楽器を演奏している人たちからすると、「音程がわかっているのにハモれないとはどういうことなのか?」「音程が分かっているのであれば、ちゃんとハモってください」と言われてしまうので、「音程がわかっている」と言う類の言い回しはボーカリストが自分自身の立場を音楽的にグループから孤立させてしまいかねない言動なので、なるべく慎まれた方が良い気がします(上から的な言い回しですみませんが、実際よくあることなのでお見知りおきをお願いいたします)。
音程はわかっているのにハモれない=音程分かっていない
上記のように音程はわかっている、しかしハモリ(コーラス)が上手にできない。
これは実は音程がわかっていないと言うことです。
わかっていると言う事は正確に音程を取れるんだ、と言うことだと今後は理解してみてください。
それでは音程がわかっている、と言うのはどういうことなのかをご説明したいと思います。
まず、音程がわかると言う理屈には大きく分けて2つあり、それが最初にお伝えした、
方法①コードに対して自分の音階がどこに行っているのか理解できる様にする。
方法②主旋律に対して自分の音階がどこに行っているのか理解できる様にする。
です。
今回のテーマの場合、絶対音感で音が取れないと言う事はご質問内容の前提条件としてありえないと考え、相対音感を軸にして話を進めて行きます。
方法①コードに対して自分の音階がどこに行っているのか理解できる様にする。
まず1つ目を考える場合、コードを理解する必要があります。
コードとは和音のことです。
楽曲を構成する上でこれは重要なもので、アレンジ上の音の重なりから、コード(和音)を感じ取るテクニックを身に付けたりする手段もありますし、自分でコード感がしっかりわかる楽器を勉強して、コードをいろいろ習得していくと言う手段もあります。
しかし最低限コーラスを取る場合はコードの流れぐらいは簡単にでも理解しておいて良いと思います。
トニック→サブドミナント→ドミナント→トニック
がどういうものであるのか理解するというのがまず手っ取り早いと思います。
- トニックと言うのはコードの流れの最も始まりの和音です。「起承転結」で言うところの起。
- サブドミナントと言うのはコードの流れで「起承転結の承」の部分です。
- ドミナントと言うのはコードの流れで「起承転結の転」の部分です。
- 最後にまたトニックに戻ってコードの流れは「起承転結の結」を迎えます。
小学校での挨拶で例えると、起立、気を付け、礼、着席、の流れが起承転結の音の流れ。
これは例えば楽曲のキーが「key=C」であった場合。
トニック→サブドミナント→ドミナント→トニック
この一連の流れは、
C→F→G→C
となります。
多分この説明だけだと何のことだと疑問を抱かれる方は結構多いと思います。
コードに触れたことがない場合は、疑問符だらけだと思います。
この場合は、申し訳ございませんがYouTubeなどでコードの基本について検索したり、勉強されてみてください。
※あくまで玄人向けの内容です、すいません。
コードの流れの基本がわかってくると、音階をボーカルが非常に取りやすくなります。
つまりそれは、コーラス…つまりハモリと言うものをテクニカルに取りやすくなると言うことが同時に言えるので絶対に理解しておいて損する事はありません。
なぜなのか…それはコードの構成音が基音・3度(Key=Cの場合、長3度)・5度(Key=Cの場合、短3度)と冒頭で書きましたね。
3度上と3度下を理解することが大事としましたが、コードを理解することがすなわち3度上下をある程度理解すると言うことに等しいなのです。
コードを理解していないと3度上とか3度下と言うものが一体どういうものなのか、肌感覚としても理解できないと思います。
ですからコードをある程度基本的なことでも良いので理解しておく事はとてもボーカルにとっても大事なことなのです。
方法②主旋律に対して自分の音階がどこに行っているのか理解できる様にする。
次に2つ目の主旋律に対して自分の声はどこに行ってるか理解する方法ですが、これは1つ目のコードを理解していれば、ある程度すぐにできるようになります。
先ほども述べましたが、3度上と3度下を理解できるようになると言う事は、主旋律に対しての3度上と3度下も理解できるようになるということです。
加えて言えば、コード(和音)からコーラスの音程が外れていなければ(ディスコードが生じなければ)、音楽のまとまりとして考えるとある程度美しいハーモニーを奏でられて言うと言うことも可能なのです。
コードの構成が3度間隔で離れている事を考えることと、主旋律から3度上下を歌える事はとても重要と言うことがいえます。
コードの構成、そして主旋律からの3度上下の音を取る。
この2つを考えなければなりません。
非常にざっくりしたアドバイスになりましたが、基本の基本は今回申し上げたような内容になります。
基本とは言えかなりわかりづらいと思いますので、その場合はまたご質問ください。
冒頭でも書きましたが、上級者(割と玄人)向けの内容となってますので、わからないからと言ってもあまり気落ちしないようにしてください。
またご質問ございましたらお気軽にご質問ください。